『やがて森になる』(九ポ堂・通常版)について
~6,000回のペダル~
小谷ふみ著『やがて森になる』には
実は三種類のものがあります。
まずは「九ポ堂・通常版」についてご紹介させていただきます。

酒井草平さんとの出会い
クルミドコーヒーから自転車で5分。
今回、「やがて森になる」の印刷をお願いした「九ポ堂」さんのアトリエは
昔ながらの国分寺の家並みの中にあります。
切り盛りされているのは、酒井草平さん、葵さんご夫婦。
草平さんは西国分寺三代目。
おじい様、勝郎さんが退職後「趣味で」活版印刷に取り組んだ名残として
その印刷室には、九ポイントの活字が並ぶ棚、活版校正機が置かれ
インクのにおいが空間を満たしています。
中でも活版校正機
(メーカーが清水製作という会社であったため、愛称は「清水サン」)は
20年弱の故障期間を経て、2012年5月に現役復帰を果たしたばかり。
縁あって草平さんをお訪ねすることになったのは、ちょうどその頃でした。
活版印刷で本をつくりたいのですけど。。
「名刺やポストカードなら刷れます。ただ本は……」
見せていただいたおじい様の本。
その文字の存在感に撃たれながら印刷のご相談をしてみるものの
草平さんからはすげないお返事。
確かに1冊分の文字を、すべて活字で組むというのは
並大抵のことではありません。
(その事情、今なら分かります……)

ただ、著者の小谷さん、発行・編集の自分(影山)ともに
同じ西国分寺三代目であることなど
勝手に縁を感じていた我々は
「九ポ堂さんにお願いしたい!」と食い下がります。
その後、何度かのやり取り
他の印刷方式の検討などを経て、あるとき。
「活字を組むのは難しいが、凸版なら……」と草平さん。
データ化した原稿を凸版に製版し、それを校正機で刷る。
前代未聞の印刷方法です。
活版校正機で刷る
「印刷」機ではなく「校正」機。
校正機とは、あくまで試し刷りのための機械。
機構は比較的単純で、小回りは利くのが長所ですが
自動紙送りの装置があるわけでもなく
1枚1枚、紙を手で差し
1回1回、足踏みペダルを踏んでの印刷になります。

さらには、印刷後の紙の裏移りを防ぐための
ブロッキング防止パウダーの散布装置などもついていませんから
1枚ごとに間(あい)紙を置いていくような手間も。
機械のサイズ的にも
一度に4ページ分の印刷が限界ということで
全220ページの「やがて森になる」を印刷しようと思ったら
55面の印刷をする必要が出てきます。
(実際には、多色刷りの面などがありますので、計58面)
たとえば、たった100冊の本をつくろうと思っても
1面ごとに最低100回(通常は1~2割余計に刷りますね)。
全面で、ざっと6,000回超はペダルを踏むということになるわけです。
200冊なら、12,000回。
300冊なら、18,000回。
同じ数だけ、紙を手で差し、間紙をはさんで……。
ほとんど苦行の領域です……。
版の位置決めや、インキの塗布量、印刷圧の調整などにも
並々ならぬ意識を使いますから
はっきり言って、僕ならやりたくありません(笑)
草平さんは、それを受けてくださいました。

贈り物とは、においや体温
思い返すのはクルミドコーヒーをつくってもらったときのこと。
2008年の夏
カフエ マメヒコの井川さんを筆頭に
毎日毎日、お店の工事を進めてくださっていたときのこと。
お店入ってすぐのところから、階段までを覆う木のタイル。
これらは、古材をひとつひとつ切って
色をつけて、オイルを塗って、パズルのようにはめて
目地を埋めて、表面を削って、またオイルを塗って……と
途方もない手間ひまをかけ、つくってくださっていました。
壁を埋める腰板も
ひとつひとつ切って
ひとつひとつ塗って
ひとつひとつ皆で貼りましたし
珪藻土も塗りました。
壁をよく見ていただくと
腰板のところ、ひとつひとつにたくさんのタッカーの穴が残っていること
見ていただけると思います。

既製品を使ってしまえば
業者に発注してしまえば
こんなに大変な思いをしなくても
そんなに違わないものは、きっとできるだろうに
なぜあえてこんな大変なことを……。
当時はそんな疑問も頭をよぎりました。
今なら分かります。
贈り物とは、においであり体温なのです。
人が、バカバカしいくらいに手間ひまかけてつくったものへの思いは
それを受け取る人の心に
きっと届くと信じています。
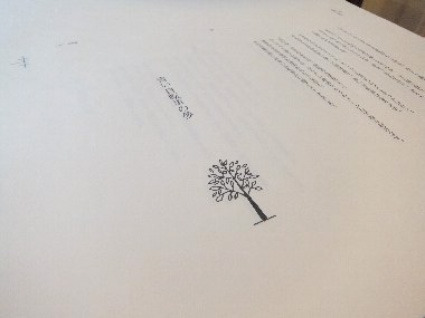
ぼくらがお店や本を
「売上を立てるため」ではなく
目の前の一人ひとりに
ちょっとした元気や希望を贈るためにやっているとするならば
そこに手間をかけることは
きっと徒労ではないのでしょう。
そしてぼくらにとって幸いであったことは
その、決して楽ではない道のりを
ともに歩んでくださる仲間と出会えたことなのだろうと思います。
(発行人)

